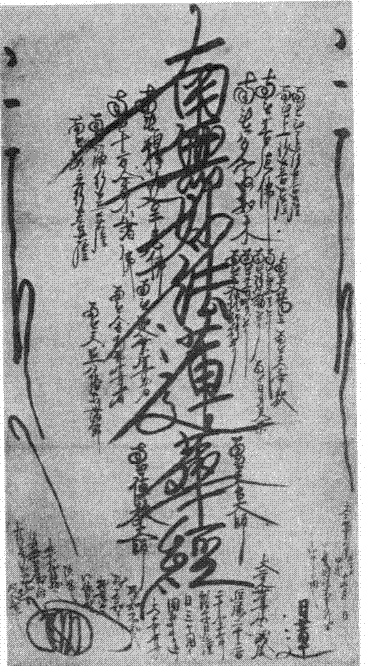㉖他国侵逼のこと
掲載の写真は千葉縣安房郡鋸南町吉濱日興門流単立妙本寺に在る通称「萬年救護御本尊」である。讃文に「文永11年太才甲戌12月 日 甲斐國波木井郷於 山中圖之」と認められている。讃文中「大本尊」と稱されたのは此の一例のみである。
日蓮大聖人は文永11年2月14日に足掛け4年の佐渡流罪をご赦免となり、同3月16日に鎌倉に到着。鎌倉幕府に呼ばれ、立正安国論に於て予言した蒙古襲来は何時になるか問われた。年内は持たないと答え、その折幕府からの蒙古調伏の依頼をお受けになるが法華経への帰依を条件とするも受け入れないので、寺領をはじめ全ての幕府からの申し出を断った。
5月12日に鎌倉を発ち、同17日現在の山梨県身延の波木井郷に到着した。そして、その年の文永11年10月5日に蒙古の船団が対馬に到来し「文永の役」と呼ばれる元寇が現実のものとなった。同14日壱岐、19日に博多に襲来するも20日には全船が引き揚げたのである。理由は定かでないが大聖人は必ずまたやってくることを憂慮して「萬年救護の大本尊」を顕わされたと推察する。
身延に入られた直後に書かれたのが御真筆である「法華取要抄」。この御書には大聖人の大切な教えが凝縮されている。月氏、漢土、日本の経論から法華経如来寿量品までの一切の甚深の事、そして要となる秘法は、本門の本尊と戒壇と題目の五字の本門の三つの法門と明記されている。
そして、弘安4年5月15日の夏至の日。身延の御草庵で開顕されたのが「第一の本尊」である。「諸天昼夜 常為法故 而衛護 大日本国」と末文に書かれているので「大日本国衛護の曼荼羅」と呼ばれ神風による蒙古調伏の曼荼羅と受け止められているのが現状である。しかし、大聖人の真の目的は、法華経を末法の世界に弘める使命を持った日本国は、今は朝廷・幕府を筆頭に謗法の国であるが、どうか大日本国の国体を護り給えという願いで「本門の本尊」をここに開顕しお隠しになり秘せしめ給われた。
「弘安の役」と呼ばれる2回目の元寇は、この1週間後の5月21日に高麗軍の対馬来襲に始まり、14万の元の大群が北九州に押し寄せたのである。しかし、7月30日のこの地方を襲った台風により元軍は海中に沈み全滅した。大聖人が元軍の兵士の調伏殲滅を大曼荼羅を掲げて弟子と一緒に祈願した考えるのは如何なものであろうか。